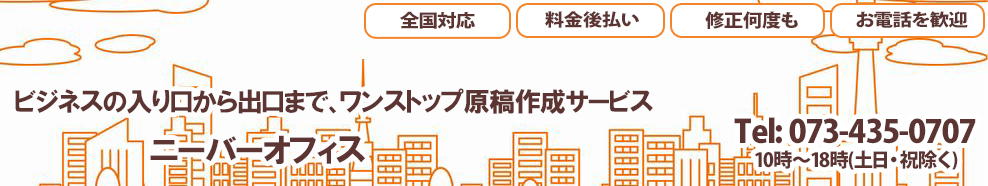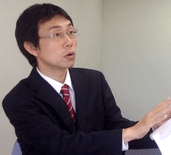昇格試験のケーススタディには、たいてい、組織のマネジメントの内容が入っています。
今回は、そのマネジメントにつながるお話です。
ケーススタディの解答を作成する際の一つの知識、一つの材料として持っておくといいのかなと思います。
それではどうぞ。
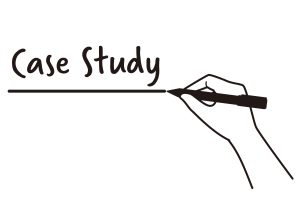
「そんな利己的な考えじゃだめだよね。」なんて軽口を言われたことはあるだろうか。
利己的な考えは抑えなきゃいけないと言うことだと思うのだが、これは一見すると「人間の本能を否定している」とも受け取れるが、実際には「利己をなくす」のではなく「利己を制御する」という意味である。
人間にはエゴがある。それを否定するのではなく、受け入れた上で調和を図ろうという態度だ。
つまり、利己心を「悪」とラベルづけしてしまえば、それを抑えることは自己否定になってしまう。
しかし「利己心はただ存在しているもの」と肯定できれば、初めてそれを抑えることができる。
利己心に善悪はなく、ただ「扱い方」の問題になるのだ。
利己と利他の間で揺れるのが人間である。
そこに無理やり手を入れ、「利己を押しつぶせ」と過度に規範化すると、人は救われるどころか不幸になることもある。
幸せにも不幸にもするのは、言葉そのものではなく、それをどう「解釈」するかだ。
だが、解釈すること自体がすでに利己の営みである。
利他であろうとすることさえ、結局は「そうありたい自分でいたい」という利己にほかならない。
むしろ、利他は利己の中に包含されている。
「利他でありたい」と願った瞬間に、それは自分を豊かにする利己の形になるのだ。
利他は利己の究極の完成形、と言ってもいいだろう。
ただし、こうした哲学を組織運営に持ち込むと途端に陳腐化する。
経営者が「利他の心」を掲げれば、それは従業員を統率するための道具になってしまう。
たとえ利己的な好意で社員が救われる面もあるにせよ、哲学は組織に入った瞬間に「規範」となり、人を縛る言葉に変質する。
哲学は「生きること」のためにある。矛盾を含むからこそ豊かだ。
一方で「働くことの規範」にしてしまうと、矛盾を排除し、貧しくなる。
ここに「哲学は個人に属するものであり、組織が所有できるものではない」という、利己・利他の考えを組織運営で用いることの宿命と限界が見えてくる。
こう思うのは利己的だろうか?
※フィクションです。